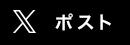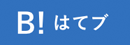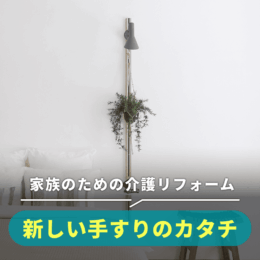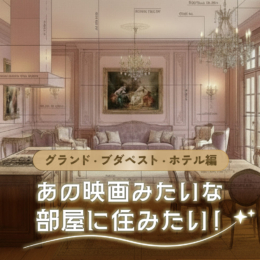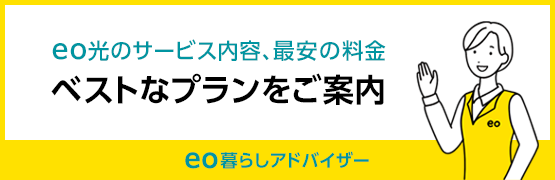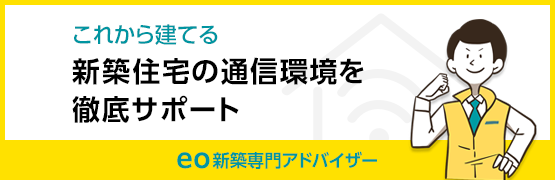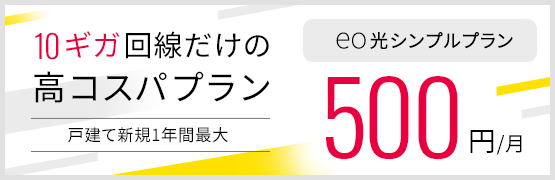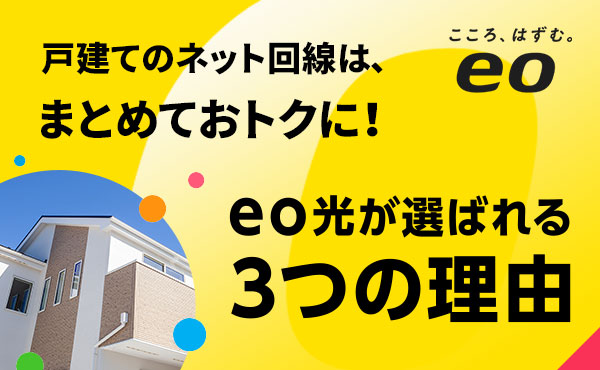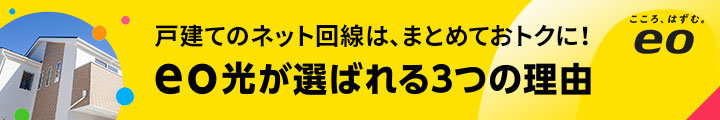公開日2025.09.11
“貼るだけ”で、白い食器をオリジナルデザインに!ポーセラーツを体験

eo光チャンネルで放送中の番組『sumica 住まいの神アイデア!』。今回は、真っ白な磁器をオリジナルデザインに変えてしまうハンドクラフト、ポーセラーツについてご紹介します。
新たなハンドクラフト「ポーセラーツ」って?

『sumica 住まいの神アイデア!』は、ナビゲーターであるお笑いコンビ・アルミカンのさおりんとマッチョ赤阪の二人が、暮らしや住まいに関するアドバイザーさんからあっと驚く“神アイデア”を教えていただくハウツー番組です。
「ポーセラーツ」という、あまり聞きなじみのない言葉…。その正体を探るべく、神戸市北区のご自宅に教室を構えるポーセラーツと絵付け講師の尾野さおりさんを訪ねました。
教えていただいたのは

ポーセラーツ絵付け講師・デザイナー
尾野さおりさん
13年前、女性誌で偶然目にしたのをきっかけに、ポーセラーツの奥深い世界に魅せられる。2013年からポーセラーツと絵付け講師としてのキャリアをスタートし、現在は自宅に構える教室「Saraha style」でレッスン講座を開催。そのほかポーセラーツの魅力や技術を広めるためのセミナーを全国で行っている。
真っ白な磁器を“キャンパス”にしたアート「ポーセラーツ」

気品あふれるティーカップに、華やかなプレート。まるで百貨店のテーブルウェアコーナーに並んでいる高級食器そのものですが、実はこれ、尾野さんがご自身で作られたものなのです。

とはいえ、カップやお皿を一から作り上げたわけではありません。まっさらな磁器に柄を貼ったり描いたりしたあと、高温の電気炉で焼きつけることで、写真のような美しいデザインの食器が生まれます。これが、今回ご紹介するポーセラーツです。
白磁を意味する「Porcelain(ポーセリン)」と「Art(芸術)」を組みあせた造語で、約30年前に日本で生まれたハンドクラフトのひとつだそう。ポーセラーツはまさに、まっさらな磁器をキャンパスに見立てた新しいアート、といえるかもしれません。

簡単で丈夫!ポーセラーツのここが魅力

尾野さんは、ポーセラーツには他のハンドクラフトにはない魅力があると言います。
ハンドメイドとは思えないクオリティ
作り方はいたってシンプルで、転写紙と呼ばれる絵柄のついたシールを切り貼りして、電気炉で焼くだけ。その簡単さに反して、高級感のある出来上がりになります。両親や友人へのプレゼントとしても大変喜ばれるそうです。

▲ 尾野さんの3歳の娘さんが作ったポーセラーツ食器。シールを貼るだけなので、とっても簡単です。
食洗機や電子レンジもOK
絵柄がすぐ剥がれてしまいそう…と思われるかもしれませんが、磁器であれば800℃程度の高温(※)でしっかり焼き上げるため、剥がれ落ちることはそうありません。食洗機や電子レンジにも対応し、食品への色移りも心配ないとのことです。
※ガラス製の食器の場合、焼成温度は570~600℃程度。素材によって適切な焼成温度は異なります。
100円の食器でも作れる
ベースに使用する白磁は、予算やデザインに合わせて自由に選ぶことができます。尾野さん作の涼やかなグラス。こちらはなんと、100円ショップで購入したものをベースに作られたそうです!(※)

ハンドメイドとは思えないクオリティと、日常的にも使える丈夫さがポーセラーツの魅力と言えるかもしれません。
※グラスの種類によっては、焼成時に破損を起こすのものもあります。見た目や表記だけでは区別がつかない場合は、使用前にポーセラーツの講師への相談が必要です。
ポーセラーツの基本は「貼る」「焼く」

作り方については、すでに軽く触れていますが、ここではもう少し深堀りします。
まずはベーシックな転写紙を使って
主な材料である転写紙は、ネットで「ポーセラーツ 転写紙」と検索すれば、さまざまな色柄のデザインを見つけることができます。1枚あたりの金額は、色の多さや顔料の種類によって変動しますが、1,500円~3,000円程度。はじめてポーセラーツをする人には、まず転写紙がおすすめです。

表現方法はほかにも!ポーセラーツの技法
転写紙だけじゃ物足りない!という人はさまざまな技法を身に付けることでワンランク上の仕上がりを目指すことができます。ここでは一部を簡単にご紹介します。

■絵具
淡い色彩やグラデーションを繊細に描くことができる。

■金彩
金や銀を用いた装飾。縁取りなどが主(きらきらとしたグリッターゴールドは食洗器や電子レンジ不可の場合あり)。

■盛り
絵柄や模様を立体的に飾る技法。エンボスとも。

■ラスター
パールのような光沢感を与えることができる技法。
焼きには「電気炉」を使用

ポーセラーツの焼き上げには、電気炉と呼ばれる装置が使われます。磁器に飾りつけを行ったあと、約800℃の炉内で焼成することで絵柄を定着させます。この電気炉は、一般家庭のコンセントでも問題なく利用できるそうです。
とはいえ、いきなり電気炉を準備するのは難しいもの。尾野さんは、より気軽にポーセラーツを楽しんでもらえるようにと、絵付け済みの磁器を送ってもらい、焼き上げた完成品を後日返送するサービスも行われています。
ポーセラーツにトライ!~白磁に転写シールで飾りつけ~

ここからは、アルミカンの二人が転写紙を使った磁器の絵付けに挑戦です。ベースに使用するのは真っ白なお皿。ここから二人の個性がどう彩られるのでしょうか…!

【使うもの】
- 左からハサミ(細かいもの切る場合は刃の細いものがおすすめ)、
ワイプアートツール
ピンセット
アートナイフ スキージー(ゴムベラ)
水(容器は転写シールの大きさに合わせて用意)

まずは転写紙の中から、使ってみたい絵柄を選びます。ファイルの中は素敵な絵柄の宝庫。一つに絞るのは、なかなか至難の業のようです…。
そこで尾野さんから「まずはテイストを決めましょう」とアドバイスが。
「可愛い系かスタイリッシュか、エレガントか…完成したデザインの方向性を決めたら、あとはピンとくるものを直感的に選ぶ!がコツです。主役になるものを一つ決めたら、それに合わせて引き立て役を選んでいきます(尾野さん)」。
赤阪さんは「モダンアート」、さおりんは「ボタニカル」をテイストに設定。そこから絵柄を直感的に選びました。

次は絵柄をハサミやカッターでちょうどよいサイズに切る作業に移ります。
赤阪さんは、一枚の転写紙でお皿を覆う大胆スタイル。転写紙の上に器をひっくり返し、フチに沿うように鉛筆で印を付けたら、ひと回り(5㎜程度)大きめにカットします。

さおりんは余白を活かしながら小さなパーツをたくさん散りばめるデザインに。柄の周りに沿ってざっくり切り取り、お皿の上に並べながらバランスをチェックします。


水を入れた容器に、切り取った転写紙の柄が上になるように浮かせてしばらく置いておきます。
指でやさしくこすり、台紙がずれるようになったら水から取り出します。転写紙本体を台紙からスライドさせるように剥がし、お皿にゆっくりと貼り付けます。

貼り付けたシールを親指の腹で優しく抑え、内側にたまった水や空気をスキージー(ゴムベラ)を使って抜いていきます。出てきた水分はティッシュで拭き取ります。

大きなシワを伸ばす場合は「温める」

湾曲した部分への貼り付けや、面積が大きい転写紙を使う場合、貼り付け面にシワができることも。そんな時は、お湯を入れたビニール袋を表面に当てて温めるとシワが伸びやすくなります。

お皿の表面からはみだした部分は、カッターを使って切り落とします。シール部分を指でしっかり押さえて、リンゴの皮をむく要領でカットします。
それぞれ黙々と作業を続けること1、2時間。これで、絵柄の貼り付けは完了です!

電気炉を800℃に設定して焼き上げます。半日~1日かけて、焼成から冷却までを行います。

これで、器の完成です!
赤阪さんはシックでおしゃれなお皿に。メガネのアクセントが個性を演出しています。

さおりんは中央のお花を主役に小さなお花をちりばめたデザイン。名前のアルファベットの切り貼りは細かな作業でしたが、難なくクリア。
転写紙を使ったポーセラーツで腕を磨いたアルミカンの二人。応用編として、グラスの絵付けや九谷焼にもトライしました。

世界初!?マッチョが描かれた九谷焼。古九谷の色彩が落ち着いた印象を演出(※焼成温度は760℃程度)。

大きなお花がポイントのグラス。どこか懐かしさを感じるデザインに仕上がりました(※焼成温度は600℃程度)。
最後に

真っ白だった磁器に自分なりのデザインを施すことで、一生使いたくなる食器を作れるポーセラーツ。
尾野さんのレッスン講座は対面方式の教室だけではなく、オンライン講座やビデオ教材などでも体験することができます。
奥深いポーセラーツの世界。興味のある方はぜひ足を踏み入れてみてくださいね。