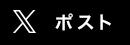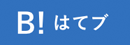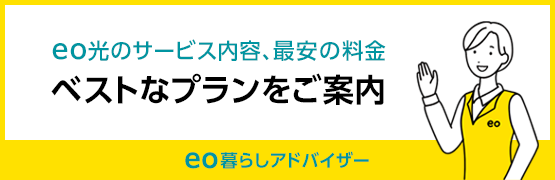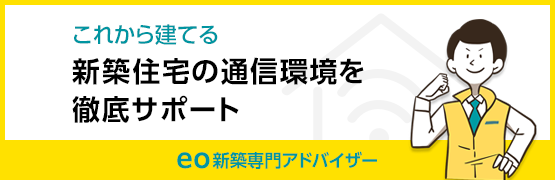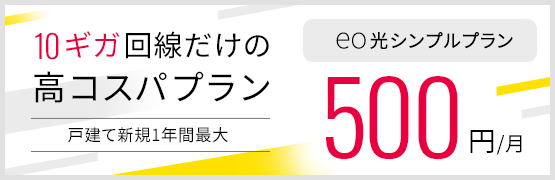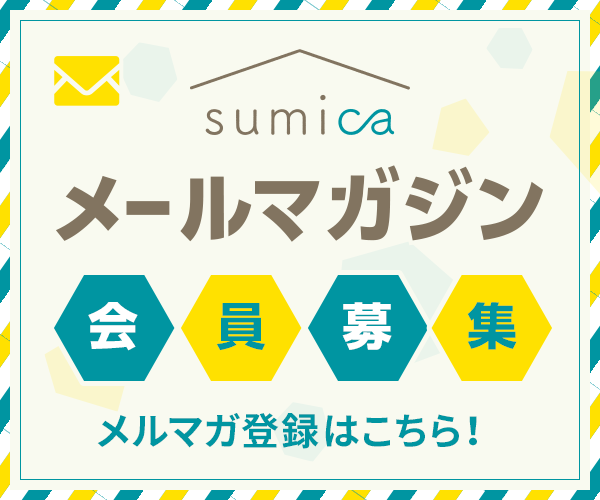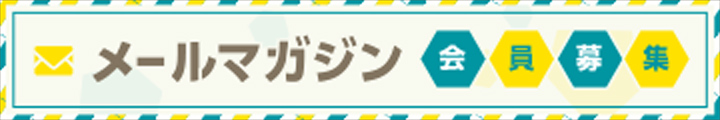公開日2025.02.18
新しい暮らしの提案。学生と家族が共に暮らすシェアハウス「ミブサンチ」

大阪府豊中市にある一軒家「MIBU SANCI(ミブサンチ)」は、夫婦と子どもたち、そして学生たちが一緒に暮らすユニークなシェアハウスです。この家では、家族と他人が共同生活を通じてつながりを深め、新しい価値観を生み出しています。今回は「ミブサンチ」を運営する壬生勇輔さん、萌さんご夫婦に、誕生の経緯や日々の暮らしについて伺いました。
学生シェアハウスが生まれた背景
緑豊かで閑静な住宅地である、豊中市。大阪大学の豊中キャンパスも近くにあるこの場所に、「ミブサンチ」はあります。約15年空き家だった一軒家を外装はそのままに、内装をまるっと改装し、壬生さん4人家族が住まいながら、学生向けのシェアハウスを運営しています。1階フロアは全て、壬生家も使うシェアハウスの共用スペース。2階の3部屋と離れの1部屋がシェアハウス用に貸し出されています。

▲ 住人の名前が手書きで書かれている表札。

▲ 「ミブサンチ」の玄関。外観は当時のまま。
「ミブサンチ」が誕生したのは、「若者たちに居場所と選択肢を提供したい」というご夫婦の強い想いからでした。家づくりを考えた時に、萌さんは大学時代の経験を振り返り、「こんな場所があればもっと人生が楽しくなるだろう」という理想の環境を具体化しようと思ったそうです。
「学生の時にいろんな大人にもっと出会いたかった。そうすればきっと将来の選択肢の幅も広がっていただろうなと。あとは大学生の頃、誰かの家に集まって話ができたり、相談する人がそばにいたりするとよかったなと思いました。こういう背景から、若者たちの将来の選択肢を広げられて、安心して暮らせる居場所を作れたらなと思ったんです」と萌さんは話します。

▲ 壬生さん家族。壬生勇輔さん、萌さん、秋水さん、清夏さん。

▲ 壬生萌さん。現在は仕事にも復帰しつつ、大学院で博士課程修学中。
物件探しが始まったのは、2020年5月でした。不動産や建築業界での仕事に携わってきたご夫婦。物件探しはお手のもの。興味も手伝って巡り会ったのが、豊中市にある15年間空き家になっていた一軒家でした。「もともと庭は荒れ果て、屋根も一部が崩れていましたが、下見をして、『リノベーションすればなんとかなる』と直感しました」と勇輔さん。
リノベーション作業は、ものづくり集団・TEAMクラプトンと共に進め、壬生さん家族だけでなく、友人や職場の人、大学時代の仲間、さらには学生たちも参加しながら行われました。これは単なる住まいの再生に留まらず、多くの人々の協力によるコミュニティづくり。延べ30人以上が作業を手伝い、その過程は「みんなで作る家づくり」というコミュニティを象徴するプロジェクトとなりました。
また内装には、自然素材を積極的に取り入れた点も特徴です。「学生たちに若いうちからいい素材に触れてほしいという思いで、無垢材や珪藻土を選びました。暮らしのなかで自然と感じてもらえるよう、私たちのできる範囲でいいものを揃えました」と勇輔さん。こうしたリノベーションを経て、2021年春に「ミブサンチ」はスタートします。

▲ 1階の共有ダイニング。食事は一緒に食べることもあるけれど、基本的には各自自由にとるスタイル。キッチンと冷蔵庫は共同で、冷蔵庫内は利用スペースが個人ごとに分けられている。

▲ 勇輔さんがDIYで作ったダイニングテーブル。「仮で作ったつもりが、意外と使い勝手良くて重宝しています」

▲ 1階の手洗い場。

▲ 2階の廊下。3部屋の個室が並ぶ。

▲ 居室の様子。壁は珪藻土で塗装されており、自然素材にこだわった快適な空間。

▲ リビングや個室の床には、無垢材を使用。
夫婦の子育てへの影響
「ミブサンチ」では、リビングを中心とした動線設計により、自然と住人同士が顔を合わせる仕組みになっています。この環境が子どもたちと学生の自然な交流を生み出しています。
現在居住している大学院生の宮村知音さんは、コロナ禍に「ミブサンチ」に入居。部活動も終了し、卒業論文のためだけに大学の研究室に通う日々が始まった頃でした。一人暮らしに飽きてきた頃で、寂しさも感じ始めていた時、大学研究室のOBだった萌さんに出会い、「ミブサンチ」に入居を決めたのだそう。

▲ お話を伺った、現在居住中の大学院生の宮村知音さん。
「帰りたくなる家ができた感覚でした。居住する学生同士で夕食を一緒に作ることもあるし、趣味が同じ学生とは一緒に出かけることもあります。リビングでオープンな催しがある時もあって、そんな時はいろんな世代の人が集まることも多いので刺激にもなっています」と宮村さん。

▲ 「プライベートな相談をすることもありますよ!」と知音さん。
またこのシェアハウスでの生活は、壬生夫婦の子育てにも多大な影響を与えています。「子どもたちも学生たちを『お兄ちゃん』『お姉ちゃん』のように慕っています。帰宅した学生たちが子どもたちと触れ合っているのは日常の風景ですね」。
また子どもたちにとっても多くの大人と触れあうことで、社会性を自然に学んでいるそう。「保育園の先生から、『他の子が人見知りするような場面でも、子どもたちは自然に接していますね』と言われました。この環境のおかげだと思います」と萌さんは話します。

▲ 1階の壬生さん家族の部屋。小さなこだわりは、スイッチの高さ。手を上げることなくオンオフできる。
育児中のご夫婦にとっても、学生たちの存在は大きな助けになりました。「育休中は、どうしても親と子どもの2人っきりになることが多かったですが、煮詰まることがあっても、学生たちとの会話がリフレッシュのきっかけになりました」と語る萌さんの言葉には、シェアハウスの利点が詰まっています。
社会還元への想い
また「ミブサンチ」の運営の核となるのは「社会への還元」というテーマです。家賃収入はあくまで生活費の補填に充てられる程度で、運営の目的は利益ではなく、若者への還元です。なんと学生が入居するとお米は無料サービスという嬉しいサービスも。「満室でも利益が出ないように設定しています。それで儲けてしまったら、僕たちの理念に反するから」と勇輔さんは笑います。

▲ 勇輔さん。さまざまなキャリアを重ね、現在はプロデューサー職。
将来的には管理人のバトンを渡し、ミブサンチのスタイルを引き継いでいける若者を見つけたいと考えています。それは家を循環させ、次の世代に引き継いでいきたいからだそう。
「家を建てる際、子どもが独立した後の空き部屋をどう活用するかは課題だと思います。それをシェアハウス(下宿)として活用するモデルが普及すれば、若者たちに居場所を提供しつつ、空き家問題の解決にもつながるかもしれません。家や暮らしを循環させるというこのスタイルが、一つのモデルとして広まれば空き家問題の解決にもつながるし、新しい住まい方の可能性も広がると思います」と2人は話します。

▲ リビングは家族と学生、訪れる人みんなの団欒の場。
「ミブサンチ」は、家族と若者をつなぐ新しい暮らしの形です。そこには、家族の成長や多世代交流、若者たちへの還元といった、さまざまな価値が詰まっています。こんな暮らし方が普及すれば、空き家問題の解決や新しいコミュニティの形成、そして暮らしの豊かさの再発見につながるでしょう。
世代を超えて、一緒に暮らす。「ミブサンチ」の試みは、未来の暮らしを描くヒントを私たちに提供してくれそうです。

筆者

ライター
小倉ちあき
企業内での広報部経験を経て、現在フリーランスのライター・インタビュアー。地域・文化・ものづくりの領域で主に活動し、今を捉えている。ジャンルの境界を越えて、有機的につなぎあわせる編集術を日々模索する。