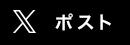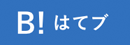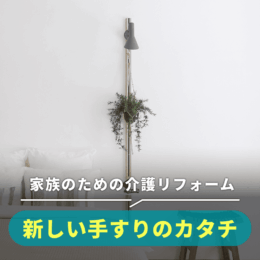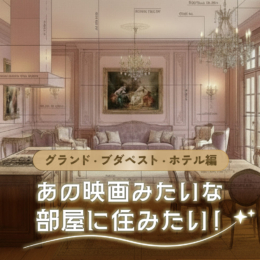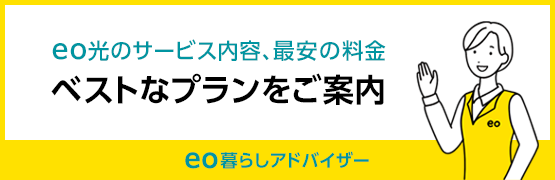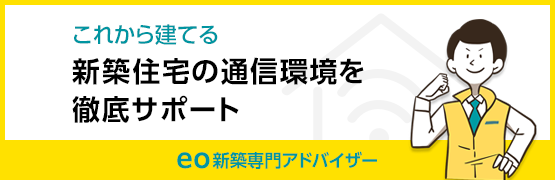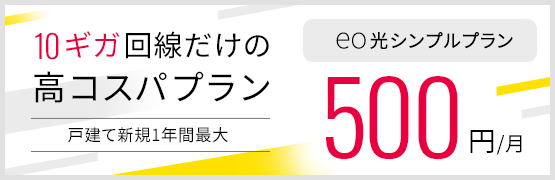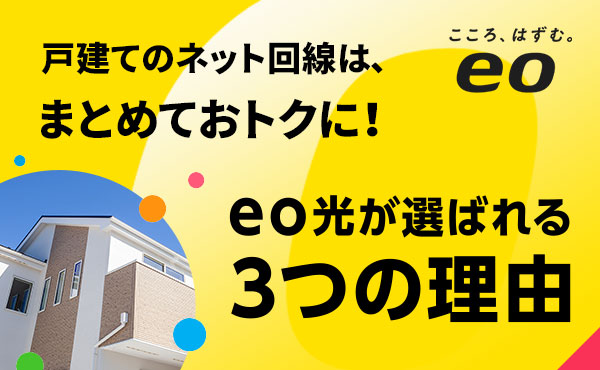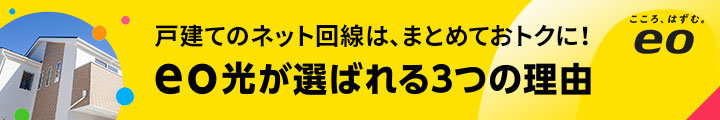公開日2025.09.19
DIY初心者がやりがちな失敗まとめ!原因と防ぐための対策も

DIYで今まで様々なものを作ってきたsumica編集部ですが、その裏では数々の失敗を繰り返してきたのも事実です。中級者になった今でも「思ったようにできない…」という失敗を経験し、時間や材料を無駄にしてしまったと落ち込むこともあります。
その経験を活かすべく、本記事では、DIYでよくある失敗例と防ぐためのポイントをまとめてみました。これからDIYに挑戦する方も、すでに経験がある方も、ぜひ参考にしてみてください。
1.ビス打ちでのよくある失敗
DIYの工程で最も頻度が多く、欠かせないのがビス打ちです。さほど難しくなさそうに思え、いざ電動ドライバーで作業を始めると思ってもいないトラブルや失敗が起きることがあります。ここでは、ビス打ちの代表的な失敗例とその対策をご紹介します。
ビスが斜めに入ってしまった…

まっすくにビスを打ち込んでいるつもりでも電動ドライバーを構える角度がずれていたり、まっすぐに押さえられていないと、ビスが斜めに入ってしまうことがあります。電動ドライバーの操作に慣れていないことが大きな原因です。ビスが斜めになると、木材が浮いてしまったり、強度が落ちてしまいます。
<対策>
- ・ビスを打つ前に下穴を開ける(下穴があるとビスがまっすぐ入りやすくなる)
- ・打ち始めはゆっくり電動ドライバーを回転させ、ビスの軸を安定させる
- ・電動ドライバーを両手でしっかり支えて、最後まで真っ直ぐに打ち込む
電動ドリルドライバーの正しい使い方は、以下の記事を参考にしてください。
操作は簡単!電動ドリルドライバーの便利な機能と使い方
ビスを打っている途中、木が割れてしまった…

細い木材や板の端にビスを打ち込むと、力が分散されずに木が割れることもあります。下穴を開けていないことや、ビスを打つ場所やビスの選び方に原因があります。
<対策>
- ・使うビスの太さに合った下穴を必ず開けるようにする
- ・ビスは板の端から少なくとも1.5〜2cm以上離れた箇所に打つ
- ・割れやすい材には「細ビス」や「スリムビス」などを選ぶ
ビスの種類については、以下の記事で詳しく解説しています。
ビスってなに?DIYに欠かせないビスの種類と選び方を詳しく解説!
ビスの頭が潰れてしまった、または頭が出っ張っている

ビスを強く締めすぎたり、電動ドライバーのビットとビスのサイズが合っていなかったりすると、ビスの頭が潰れる(ビスの頭がナメるとも言います)ことがあります。ビス打ちではとても多い失敗の一つです。
また、途中でビスが止まってしまい、頭が出っ張ってしまうケースもあります。これは仕上がりが悪くなるだけでなく、他の部材が頭に当たることでガタガタになったり、ケガの原因にもなってしまいます。
<対策>
- ・ビスに合うビットを選ぶ
- ・ドライバーの回転力(トルク)を調整しながらビスを打つようにする
- ・最後は軽い力で調整しながらビスを締めるようにする
これらのビス打ちの際に起こる失敗は、以下3つが原因で起こることがほとんどです。
・下穴を開けず、直接打ビスをち込んでいる
・電動ドライバーの力加減を誤っている
・木材とビスの相性を考えていない
正しい道具選びと、「丁寧に焦らず、慎重にまっすぐ」を心がけるだけで防げます。結果的に作業効率も仕上がりも良くなりますので、常に意識しておきましょう。
2.「買いすぎた」「足りない」材料での失敗

DIYを始めたときに意外と多いのが、材料を買いすぎた、または足りなくなることです。設計を曖昧にしたまま買い物をすると、木材やビスのサイズ、本数を間違えて足りずに作業が止まったり、材料が余って無駄になったりしてしまいます。
材料を買いすぎた
足りないことに対する不安や、余ったらまた何かに使うだろうという考えで多めに木材や金具を購入してしまうと、材料が大量に残ってしまいます。費用がかさむうえ、さらに収納場所までも圧迫し、結局処分する羽目になります。
<材料の買いすぎを防ぐには>
- ・必要な寸法を事前に測り、設計図や木材カット表、必要な材料リストを作成する
- ・必要な分+少しだけの余裕を持って購入する。足りなければ追加で購入する
特に塗料を多く買いすぎた場合、保管には注意が必要です。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
DIYでのワックス・オイルの取り扱いには注意!正しい保管方法
材料が足りない
設計図を用意しない、また簡単な設計図だけでお店に行くと、「木材の本数が1本足りなかった…」というようなことが起こります。そうなると作業を中断し、再びお店へ行く手間と時間がかかり、作業効率は大幅にダウン。さらに工作意欲の熱が冷め、やる気もなくなってしまいます。これは結構、あるあるです。
<材料の準備不足を防ぐには>
- ・設計図をしっかり作り、事前の準備は丁寧に怠らないようにする
- ・どこにどの材料を使うか、わかるように書いておくと数量の間違いが防げる
- ・必要な分+少しだけの余裕を持って購入する。特にビスや釘など消耗品は多めのほうが安心
初めてでも設計図は簡単に描くことができます。詳しくは以下の記事を参考に。
【失敗しないDIY】設計図は意外と簡単?手描きとExcelを使った描き方
3.設置ができない!測ったつもりの「採寸ミス」

棚や収納を作り、いざ設置しようとするとサイズが合わず木材が入らない、材と材に隙間が開いてしまったというのもよくある例です。これらは採寸ミスが原因です。
大体このくらいだろうと目測で決めてしまったり、採寸の際にスケール(メジャー)を斜めに当ててしまっていたり、また一度しか計測をしていないので間違えたままになっている、といったところでしょう。家具を壁際や狭いスペースに設置する場合、この数ミリの誤差が致命的になります。
<対策>
- ・採寸は必ず2回以上して、しっかり記入しておく
DIYの楽しみは、採寸を丁寧にすることで得られると言ってもいいでしょう。事前の注意を徹底することで、完成後の満足度が大きく変わります。また、やり直しの手間と材料の無駄も防ぐことができます。
4.塗装のよくある失敗「ムラ・剥がれ・ベタつき…」
自分好みの色にしたい、家具や部屋の雰囲気を変えたいと塗装する方が多いと思いますが、実際には「塗りムラができて目立つ」「剥がれてくる」「ベタベタして使えない」といった失敗も多いのも事実です。その原因を見ていきましょう。
塗りムラができて目立つ

塗装面がムラになってしまう原因は意外とシンプルです。刷毛やローラーに塗料をつけすぎていたり、逆に少なすぎたりすること。また、下地処理をせずに直接塗料を塗っていたり、一度しか塗布していない(しかも厚く塗り過ぎている)ことが原因です。
<対策>
- ・下地を整える
サンドペーパーで表面を軽くこすり、さらにプライマーなどの下塗り材を塗っておくと、塗料のノリが格段に良くなる - ・一度に厚塗りせず、薄く均一に塗るのがコツ。2~3回重ね塗りする
- ・適当に様々な角度から塗るのではなく、刷毛やローラーは同じ方向に塗るとムラができにくくなる
刷毛とローラーでの塗装の仕方は、以下の記事を参考にしてください。
【DIY塗装】刷毛、ローラー、スプレー、塗る面積や用途で変わる塗装の仕方
塗装が剥がれてしまう

「塗装が剥がれてしまう」これも塗装でよくある失敗です。下処理が不足していたり、塗料選びでのミスが原因のことが多いです。
例えば、ホコリや手垢、油汚れが残ったままの材料に塗装すると、塗料がしっかり密着せず、時間が経つと剥がれやすくなります。また、木材・金属・プラスチックなど、それぞれの素材に適した塗料があり、間違った塗料を使うとしっかりと定着せず剥がれやすくなります。重ね塗りをする際は、塗料が完全に乾く前に重ね塗りをしてしまうと、下の層が浮き上がり剥がれる原因になります。
<対策>
- ・塗装面にホコリがついている場合はしっかり落としてから塗装する
汚れがひどい場合は中性洗剤やアルコールで拭き取る下地処理をすると尚良い - ・それぞれの素材に適した塗料を選び、使用することが大切
- ・塗料の指定乾燥時間を守ってから重ね塗りをする
塗料の選び方は以下の記事を参考にしてください。
【プロが解説】DIYで木材に使う塗料の違いは?代表的な5つを比較!
仕上がりがベタつく
塗装した面がベタベタしてしまうという失敗例もあります。これは塗装のタイミングと環境が大きく影響しています。乾燥時間を守らずに重ね塗りをすると、層が重なった部分が乾かずベタつきの原因になります。また塗料を乾かす環境の湿度が高かったり気温が低いと、塗料が乾きにくくベタつきやすくなります。ベタつくことでさらに、塗膜の劣化を引き起こすことにもなります。
<対策>
- ・塗料パッケージや説明書に記載されている乾燥時間を守る
- ・重ね塗りをする時は必ず乾いた状態で行う
- ・湿気の多い日は塗装を避け、晴れた日や換気が良く、風通しの良い場所で塗装する
DIY初心者がミスを防ぐためのポイント
最後に、初心者の方がおさえておきたいポイントをまとめました。
【1】正確な採寸を行う
まずは木材や材料・部品のサイズを数回確認し、採寸ミスを防ぎましょう。「測ったつもり」の油断が設置時の失敗につながります。
【2】事前準備を徹底する
作業前に設計図を用意し、必要な工具や材料をリスト化して確認しましょう。準備が整っていることでスムーズに工程が進み、作業の効率もアップします。
【3】塗装では下処理・下塗りを丁寧に
ホコリや手垢、油汚れをしっかり落とし、ヤスリがけやプライマーなどの下処理をしっかり行いましょう。塗装後の仕上がりに差が出ます。
【4】組み立て・設置作業は丁寧に焦らず、慎重に行う
下穴を開ける、正しい道具や材料を選ぶするだけで、作業の効率も仕上がりも良くなります。
まとめ
今回紹介した「失敗例」は、DIYをしたことがある人はみな通る道です。これらを繰り返すことで知識や技術が身に付き、上達すると言ってもいいでしょう。楽してDIYはできません。
面倒に感じる作業や工程ほど、仕上がりを左右します。準備と計画をしっかり行うこと、失敗を恐れず対策を意識しながら進めることで満足度の高い仕上がりになるはずです。失敗も楽しむ、それがDIYです。
筆者

sumica編集部
自然体で心地いい時間が過ごせるおうちにしたい、そんな想いを込めて、「こんなのあったらいいな」「これは便利!」と思う暮らしのアイデアをお届けします。