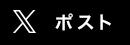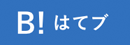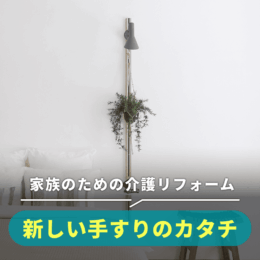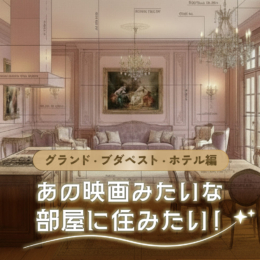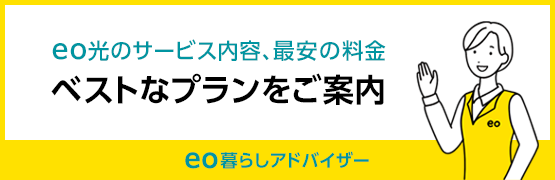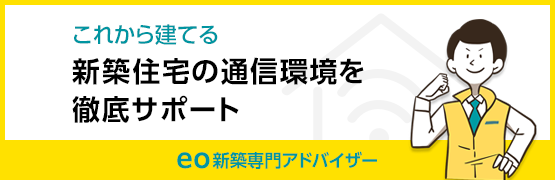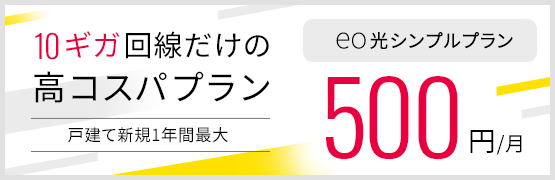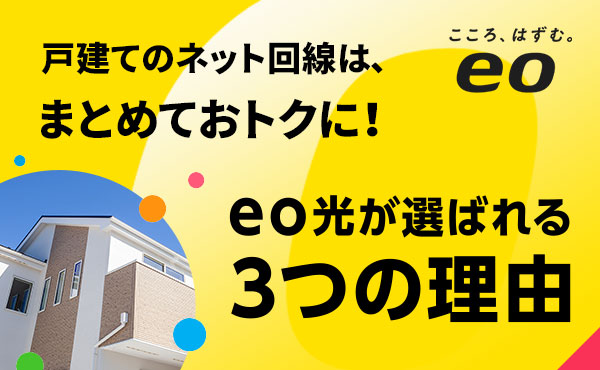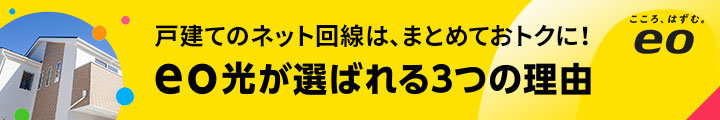公開日2025.03.28
昔ながらの文化住宅をリノベーション、住人が程よくつながる賃貸住宅へ

シェアハウスは少し気が引ける、一人暮らしも少し心細い…。そんなあなたにぴったりの暮らしをご紹介します。
築約60年の文化住宅をリノベーションして生まれ変わった「はちふく文化GAMO-4」は、一人暮らしとシェアハウスの良い部分を兼ね備えた新しい賃貸住宅です。昔ながらの文化住宅の魅力を生かしながら、住人同士が程よくつながる仕組みが整っています。今回は、このプロジェクトを手がけた福永工務店の視点と、実際に暮らす住人の声を通して、文化住宅の新たな可能性を探ります。
文化住宅のリノベーションと再生の背景
大阪市城東区に位置する「蒲生四丁目」は、歴史と現代が融合する活気あるエリアです。交通アクセスが良く、ローカルな魅力を残しながら発展を続ける街に、2024年10月、「はちふく文化GAMO-4」が誕生しました。
「はちふく文化GAMO-4」は、築約60年の文化住宅をリノベーションした、A棟とB棟合わせて8戸ある賃貸住宅です。

▲ はちふく文化GAMO-4の外観。左側がA棟、右側がB棟。

▲ A棟、B棟合わせて、建物内には全部で8戸の住宅がある。出入や来客はオートロックのモニター付きインターホンで管理できて、セキュリティ機能もばっちり。
かつての文化住宅は、住人同士の距離が近く、自然な交流が生まれる場所でした。しかし、現代の賃貸住宅は個の空間が重視され、隣人との関わりが希薄になりがちです。「はちふく文化GAMO-4」では、その良さを残しながら、現代のライフスタイルに適応した設計が施されています。その結果、「一人の時間を大切にしながら、ちょうど良い距離感で人とつながる」住まいが実現しています。

▲ ドアを開けて入ると土間広場が。ここは住人の共有スペース。

▲ 天井から差し込む自然光で、共有スペースは明るい。
このプロジェクトのきっかけは、長年放置されていた文化住宅について、福永工務店が大家さんから相談を受けたことでした。福永工務店に勤務する裕美さんと大樹さんは、実の姉弟で共に一級建築士。「文化住宅の価値を残しながら、新しい暮らし方を提案できるのではないか」と考え、この文化住宅を譲り受けることを決意し、長屋再生プロジェクトはスタートしました。

▲ 左から、福永工務店の福永大樹さん、裕美さんとそのお子さん。
「文化住宅はかつてはどこにでもありましたが、最近ではどんどん減っています。しかし、外観には風情があり、現在の建物にはない魅力が多いのも事実。リノベーション次第で、まだまだ魅力的な住まいに生まれ変わる可能性があると考えました」と大樹さんは話します。
「はちふく文化GAMO-4」は、「文化住宅」という概念を現代のライフスタイルに合わせて再定義したプロジェクトでもあります。たとえば土壁や梁など、もともとの建物の雰囲気を残しながらも、耐震性を向上させる工夫を採り入れています。「文化住宅は、古いからこそ価値があります。ただ新しくするのではなく、当時の面影を残しながらブラッシュアップするかにこだわりました。どの部分を残し、どこを新しくするのか。そのバランスを取るのが最も難しい作業でした。二人で意見を出し合い、現場で都度確認しながら調整したことで、満足のいく仕上がりになったと思います」と振り返ります。

▲ 当時の土壁は残したまま。

▲ 各所に残された土壁や梁から、文化住宅だった軌跡が感じられる。

▲ 古いのものを残しながらも耐震補強はしっかり施されている
築約60年の建物は、そのままでは現代の生活に適していません。耐震性や断熱性の向上はもちろん、設備も今の暮らしに合わせて整える必要がありました。特に注目したのが、「共有スペース」のあり方でした。
「当時の文化住宅では、隣人同士の距離が近く、日用品の貸し借りをしたり、縁側でおしゃべりをするのが日常でした。しかし現代の住まいでは、そうした人と人とのつながりが減っています。それならば、今の時代に合った“ちょうど良い距離感”のつながりが生まれる住まいを作りたいと考えました」
すべての部屋を完全に独立させると、普通のアパートと変わりません。そこで隣り合う3軒の住戸の真ん中の1軒を取り除き、住人が自然と交流できる「共有スペース」にアレンジ。「普段の生活のちょっとしたプラスアルファとして活用できたり、気分転換に使ったりできる空間になっています」と裕美さん。

▲ 2階は土間にある階段を上がって、渡り廊下を歩いて各部屋に入る。

▲ 部屋は全て、単身層を想定して設計されている。2階部屋はロフト付き。一部の部屋にはウォークインクローゼットもある。
共有スペースがつなぐ、適度な距離感と心地よさ
「はちふく文化GAMO-4」に住む松本侑伽さんは、当初は普通の賃貸を探していました。しかしこの物件を見つけた瞬間、「ここに住みたい」と直感したといいます。

▲ 住民の松本侑伽さん
「普通の賃貸は壁に囲まれ、閉鎖的に感じることが多いのですが、ここは木材がふんだんに使われていて、吹き抜けもあり開放感があります。最初に見たときから、この空間がとても心地よく感じました」と松本さん。

▲ 松本さんのお部屋は、B棟の1階奥。
「前の住まいでは、隣人の顔も分からず、誰が住んでいるのかも知らないままでした。だから、家に帰るとどこか閉塞感がありましたが、ここに引っ越してからは、家に帰るのが楽しみになりました。たまに生活音が聞こえるのも良いですね。たとえば洗濯機の音がしたり、ドアの音がして『帰ってきたのかな』と感じられたりする人の気配は安心感につながっています」

▲ 各戸の間取りは1LDK。オリジナルキッチンで2口のIHコンロ。

▲ 文化住宅の面影を残す、窓。全室二重サッシで気密性も高い。

▲ 全室シャワーブース。
また普通の賃貸では3~4人集まると窮屈になりがちですが、共有スペースを活用することで、友人を気軽に招くことができます。
「先日はたこ焼きパーティーを開きました。遊びに来てくれた友達の反応もとても良かったです。引っ越しを検討する際に、シェアハウスは少しハードルが高いと感じていました。人と関わるのは好きですが、毎日関わる必要があると負担に感じてしまうこともあります。ここなら一人の時間を確保しながらも、必要なときには助け合える関係性が築けると感じています」

▲ 福永さんたちと松本さんの交流も多い。「大家さんが身近なことも安心材料です」と松本さん。
また、住人同士で「こんにちは」「おかえりなさい」と自然に声をかけ合う場面も日常の風景。まるで小さなコミュニティが生まれているようです。「お互いの気配を感じながらも、干渉しすぎない距離感がちょうど良いですね。普段はそれぞれ自由に過ごしつつも、困ったことがあれば助け合える安心感があります」。この「共有スペース」は、強制的な交流を求めるものではなく、自然なつながりを生み出しているようです。
「余白のある住まい」が生む、顔の見える暮らし
リノベーションでこだわったのは、「住まいの中に余白を残すこと」。「一般的な賃貸住宅は、すべてが完成された状態で提供されます。しかしここでは住人が自由に空間を活用できるよう、あえて余白を意識して設計されています。共有スペースは住人同士が自然に交流し、活用できる場になりつつあります」
「隣に暮らす人の顔が見える暮らしって良いですよね。最近では住人同士で新年会を開いたり、フリーマーケットを開催したりしました。ご近所にある喫茶店からケータリングをお願いしたり、マーケットに近隣のショップの方が参加してくれたりと、地域の方との交流も生まれつつあります。住人さんが自主的に場を活用することで、暮らしの可能性がどんどん広がっていくと嬉しいです」と裕美さん。

▲ 2025年1月に行われた新年会の様子。写真提供:福永工務店

▲ 2025年3月2日に開催された、フリーマーケット「福ノ市」の様子。
住人同士の情報交換には、オンラインアプリを活用。LINEグループで共有スペースの利用時間を決めたり、イベントの告知をしたりすることで、無理なくコミュニケーションを取れる仕組みができています。またお子さんのいる裕美さんは、子どもと一緒に数ヶ月間暮らし、暮らしの魅力をSNSで発信していたこともありました。実際に暮らすことで、住人が快適に暮らせるように住環境を整えるきっかけにもなっているそうです。

▲ 「生まれたばかりの物件ですが、これからどのように育っていくのか、私たちも楽しみです」と裕美さん。

▲ 床はすべて無垢のフローリング。裕美さんがお試しで暮らしていた部屋。「ここはミニマリストなら2人暮らしも可能な設計になっています」

▲ この部屋のキッチンは引き戸で仕切られている。部屋からキッチンが見える設計。
文化住宅をリノベーションし、新たなコミュニティを生み出したこのプロジェクト。住人同士が程よくつながることで、心地よい住環境が生まれています。程よい関係が生まれる、ちょうどいい暮らし。昔ながらの文化住宅の魅力を活かしつつ、現代の暮らしにフィットさせる。この試みは今後のまちづくりや住まいの在り方に、新たな可能性をもたらすでしょう。
取材協力
福永工務店
大阪市住之江区で、住宅を中心に新築やリノベーションの設計から施工までを手がける。「はちふく」はリノベーション部門。暮らす人や建物オーナー様のひととなりがにじみ出るような空間づくりを心がけている。